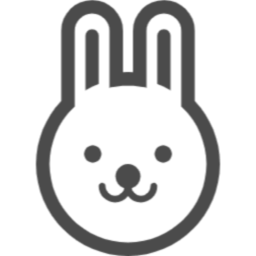
辛いときの乗り越え方や上の子への関わり方も教えてほしいです
こういったお悩みをもつかたにお話していきたいと思います。
また、2人育児という言葉にとらわれず、一人目の子どもや、2人より多いきょうだいの子育てにも通用する内容かと思います。
この記事の内容
- 2人育児の辛いところ
- 辛い2人育児の乗り越え方
- 2人育児をしていく上で気をつけたいところ
- 上の子へのかかwり/-++*-
現在この記事を書いているわたしは、6歳と1歳の男の子のママをしています。
きょうだいは4学年差があり、下の子が生まれたときにはコロナ禍。
上の子はママに甘えたい気持ちと、弟と遊びたい気持ちと、いろいろなモヤモヤしたもので機嫌が悪かったです(笑)
そんな感じでスタートした2人育児。
2人育児はつらい、ならどうやって乗り越えていけばよいのかを知っておくだけで心の持ちようが変わってくると思います。
ぜひ参考にしてくださいね。
もくじ
2人育児の辛いところ

子育てになれた頃にやってくる二人目の子育て。
他の人と年の差は違えど、子どもが二人になるということは大きな変化ですよね。
具体的にどういった辛いことが待っているのでしょうか?
2人の生活リズムが違う
これはきょうだいの年の差が離れれば離れるほど生活リズムが大きく変わってくるでしょう。
とくに、寝かしつけや、沐浴時期のお風呂問題、離乳食期のご飯、、、などと、考えるだけでこれだけのことにきょうだい間でズレが出てきます。
ましてや、ワンオペで子育てしている家庭だと、手伝ってもらう手がなく、ママひとりで2人のお世話をしなくてはなりませんよね。
上の子が赤ちゃん返りをする
赤ちゃん返りとは:ある程度大きくなった子どもが赤ちゃんのように甘えたりわがままを言ったりすることを言います
よく、下の子ができると、上の子が赤ちゃん返りをすると言われています。
(一人っ子でも環境によって赤ちゃん返りをする子もいるそうです)
下の子のお世話をしているのに、しっかりしてほしい上の子が甘えたりわがままを言ったりしてきたら、余裕を持って接することが難しいですよね。
上の子がかわいく思えない
『上の子かわいくない症候群』という名前もつけられるほど、二人目を生んだお母さんが多く通る道です。
わたし自身も経験があります。
今まで我が子が一番かわいいと思っていても、下の子ができてお世話していくうちに、あれ?なんか可愛いと思えやんくなってる?と自分の気持ちに気づき始めます。
この現象に原因はないらしいのですが、「自分の子をかわいいと思えない」という自分の気持ちに罪悪感を感じてしまいます。
体力が追いつかない
これは、出産するごとに年をとっていってるから当たり前ですよね。
21歳で上の子を出産したときは若さで乗り切れても、26歳で二人目を出産したら、一人目のときより体力はなくなっていますよね。
合わせて二人の子育てをしていくとなれば、より体力がいるので精神面だけでなく体力面でも大変になってきます。
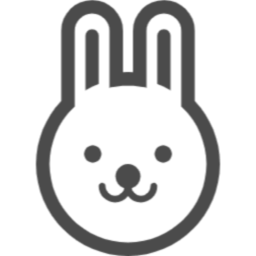
二人育児の乗り越え方

子どもが二人になる。
自分が年をとっている。といった大変なことばかりだと思われがちですが、ちょっとした工夫でその大変さを乗り越えることができますよ。
それは4つあります。
- 夫と協力する
- 家事はほどほどに。たまには手を抜く
- お金をかけてもグッズやサービスに頼る
- 寝れるときに寝る
詳しく一つずつ見ていきましょう。
夫と協力する
子どもが一人の時、夫は子育てに協力してくれていますか?
それとも、仕事で忙しく、ほとんどママがお世話をしていましたか?
父親が一人目のときにお世話したがらないという理由に、「どうすればいいかわからない」という声が多いそうです。
「どうすればいいかわからないから母親にしてもらおう」という気持ちなんでしょうね。
なので、もし一人目のとき、全然お世話してくれなかったから…と、二人目の子育てもママが一人で抱え込むのは良くないですよ。
おむつの替え方やミルクの作り方、抱っこしててほしいなど、言葉にして伝えていくことで、夫もどのようにすればいいのかを知ることができます。
このようにお世話の方法がわかれば、夫も協力してくれることが増えてきます。
一人目のときに、どうすればいいかわからないという理由で傍観しているだけの夫も、見て学んでいるはずです。
そこに言葉で方法を伝えてあげれば学んでいってくれるはずです。
わたしの夫も、一人目のときはおむつさえ替えてくれなかったけど、手本を見せて伝えるように心がけました。
すると、二人目になると気持ちのもちようも違うのか、積極的にお世話してくれるようになりました。
伝えるって大事ですね^^
家事はほどほどに。手を抜けるところは抜こう!
これは二人育児に限らず主婦であるママすべての方に言えることでしょう。
生きている以上、体が資本です。
体を壊してしまったらなにもかもがうまくいかなくなりますよね。
そうなる前に、しんどいときは手を抜くことを心がけましょう。
ときには便利な家電に頼ったり、冷凍食品や惣菜を活用したり…
ママがしんどそうだと、子どもも不安になっちゃうので、元気なママでいられるように自分をコントロールすることが大切ですね。
多少お金をかけてもグッズやサービスに頼ろう
上記と同じような内容になりますが、頼れるものは頼りましょう。
甘えるのが下手っぴなママでも、喋らない家電になら頼ることは簡単ですよね。
スイッチを押すだけでお掃除してくれるロボットを始め、洗濯機や乾燥機を活用したり、食器洗い乾燥機で食器洗いの手間を省いたり…
家電に頼ることで自分が楽になるだけでなく、本来しなければならなかった家事をする時間が浮きます
その時間を子どもとの時間にすることができ、子どももハッピーになりますね。
寝れるときに寝る
子育てに寝不足はつきものですよね。
夜泣きがある子なら夜ぐっすり眠ることができないですよね。
よる眠れないなら、昼に眠れそうな時間をみつけて寝るようにしましょう。
子どもと一緒に昼寝する
上の子にテレビを見せておいて下の子と一緒に寝る
夫に二人任せておいてママひとりで寝る
移動中車で子どもが寝たらママも運転席で一眠りする
考えたら少しでも寝れる瞬間はたくさんありそうです。

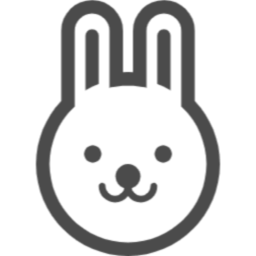
上の子とこれからどう関わっていけばいいのかな
上の子へのケアを心がけましょう

ママのおなかのなかに赤ちゃんがいるということをわかっていても、生まれていざ目の前に「おとうとよ」「いもうとよ」とあらわれても、混乱してしまいますよね。
かわいがっていた友人の子どもが、実はあなたの子だったんですよと言われるようなものです。(例え下手くそですね)
混乱しながらもお兄ちゃん・お姉ちゃんになった上の子にはどのように関わっていってあげたらいいんでしょうか
上の子との時間を意識して作る
上の子はとってもかわいいから、下の子が生まれてからも絶対二人共かわいがれるわ!と思いますよね。
でも現実は下の子のお世話で手一杯、寝不足でメンタルもやられて上の子のことを全力ではかわいがれなかったです。
なので、上の子との時間を「意識して」作るのが大切だと思います。
二人でお出かけするのもいいですが、下の子が小さいときは、ママも離れにくいですよね。
そんなとき、上の子と同じ遊びをしたり、寝る前に子どもが選んだ絵本を一緒に見るなどなど、その子がしたいことを一緒にしてあげるようにしていました。
それでも甘えん坊になっていたのは変わりないですが、一緒になにかするだけで嬉しそうで、それを見た自分もかまってあげられない罪悪感が薄れていたように思います。
お兄ちゃん・お姉ちゃんの押し付けをしない
おとうとやいもうとが生まれたら自動的に「お兄ちゃん」「お姉ちゃん」になる子どもたち。
あなた自身が長男長女だったとして「お兄ちゃんなんだから」「お姉ちゃんなんだから」といろいろなことにつけて我慢をさせられることがあったら、どう思いますか?
わたしなら「スキでお姉ちゃんになったわけちゃうのに」と反抗したくなるし、わたしのことをわかってくれていないと思い、悲しくなります。
下の子が生まれただけで何かが上達したり学びが増えたりするわけではありません(生まれたことにより意識はあがるでしょうが)
「お兄ちゃんなんだからだめでしょ」
「お姉ちゃんなんだからしっかりして」
などと、お兄ちゃん・お姉ちゃんの役割を押し付けるような言い方は気をつけたいですねお兄ちゃん・お姉ちゃんの役割を押し付けるような言い方は気をつけたいですね。
反対に、「さすがお兄ちゃん」「やっぱりお姉ちゃんだね」などのその子を持ち上げるような尊重する言葉がけは意識があがって他のことも頑張ろうという気持ちになるはずです^^
「仲良くしてくれて嬉しい」と伝える
年の離れたきょうだいだったら、上の子が譲ってあげるという場面が多いです。
しかし、年が近いと、仲良く遊んでいたのにケンカに…という話をよく聞きます。
ケンカが悪いわけではありません。
子供同士の気持ちのぶつけ合いや手加減を学べる機会でもあります。
お兄ちゃん・お姉ちゃんが下の子を思いやる気持ちを育てたいのなら、仲良く遊んでいるときやお世話してくれているときに、「ありがとう」「嬉しい」とポジティブな言葉をかけてあげましょう。
ポジティブな言葉をかけられた子どもは、仲良く遊ぶことでママが喜んでる!お世話すると嬉しいんだ!と学ぶことができます。
そういう経験から下の子に優しくできる、思いやれる気持ちを育てていけると思います。
下の子の犠牲にさせない
つまり、下の子が泣いていて上の子のことをかまってあげられないとき…「〇〇が泣いてるから遊べないの」などと話すのは、下の子がいる=ママとあそべない という感情を持ってしまいます。
このようなときは、「〇〇が泣いてておっぱいあげるから、それが終わったら遊ぼうね」と、下の子がいる=泣いたらおっぱい=終わったら遊べる と考え、下の子のことを悪く思わず、またいつ遊べるかが具体的にわかり、安心して待つことができます。
なんだか難しそうですよね。
簡単に言うと、上の子が下の子を妬まないように気をつけてあげる。というのが大事かと思います。
まとめ:下の子が生まれたら上の子をかわいがろう
 二人育児の辛いところとその乗り越え方をお話しました。
二人育児の辛いところとその乗り越え方をお話しました。
一人でも大変だと思っていた子育てが二人になるともっと大変!?と思いますが、実際二人育児をしてみると楽しいことばかりです^^
上の子へのケアをしてあげることで、上の子の年齢にもよりますが、たくさんお手伝いしてくれるようになります。
「さすが」という褒め言葉を使いながら、上の子の意識を上げ、下の子のお世話をしつつ、上の子をめいいっぱい、かわいがってあげてくださいね。
